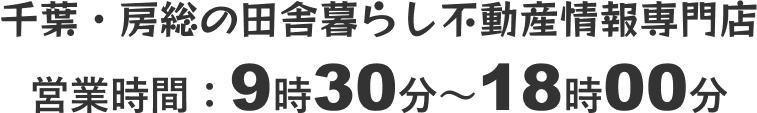「親から土地を相続したけれど、名義変更はまだ済んでいない」「都会に住んでいて実家はもう何年も空き家…」「相続手続きが難しそうなので、つい後回しにしている」
もし上記に当てはまるなら、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化を知らずにいると、思わぬペナルティや損失を招くことになるかもしれません。
そこで本記事では、千葉県房総エリアに拠点を構える、当社「東栄建設株式会社」が相続登記の義務化についてわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みください。
目次
相続登記の義務化とは?
改正不動産登記法の施行により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を申請する必要があります。怠れば10 万円以下の過料(行政罰)の対象になる可能性があります。
「うちは何十年も前に相続したから関係ないだろう」と思われるかもしれませんが、この義務化は過去の相続にも適用されます。
つまり、法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続であっても、まだ登記が済んでいない不動産はすべて対象となり、施行日から3年以内に登記を済ませる必要があります。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
所有者不明の土地は、全国で九州エリアよりも広いとされ、公共事業の妨げや防災上のリスクが顕在化しました。
また、管理されずに荒れ果てた空き家は、景観を損なうだけでなく、倒壊の危険や防犯および衛生上の問題を引き起こす原因にもなります。千葉県房総エリアも例外ではありません。
例えば、総務省「平成30年住宅・土地統計調査」によると、いすみ市では「使用目的のない空き家」が 2,680戸、空き家率13.1%と報告され、全国平均(約 5.6%)の倍以上です。
また、鴨川市は空き家率が20%台後半で推移しており、千葉県内でも高水準が続いています。
2025年6月に公開された「ダイヤモンド不動産研究所」の調査によると、千葉県全体の空き家率は12.35%で全国41位になっていることがわかっています。さらに、千葉県房総エリアの一部自治体は県平均を大きく上回っています。
相続登記をしないとどうなる?
「10万円以下の過料を払えば済む話ではないか」と軽く考えてしまうと、さらに大きな問題に直面する可能性があります。相続登記をしないことのリスクは、金銭的なペナルティだけにとどまりません。
まず、不動産を自由に処分できなくなります。登記簿上の名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売却することはもちろん、誰かに貸したり、担保に入れて融資を受けたりすることもできません。つまり、資産として活用する道が完全に閉ざされてしまい、ただ固定資産税だけを毎年支払い続ける「負の資産」と化してしまいます。
また、相続関係が複雑化し、解決が困難になります。相続登記を先延ばしにしている間に、もし相続人の誰かが亡くなってしまうと、その方の子どもや孫が新たに相続人となります。
世代が進むごとに相続人の数は増えていき、面識のない遠い親戚まで含めて全員の合意を取り付けなければ、不動産の処分ができなくなってしまいます。話し合いがまとまらず、法的な紛争に発展してしまうケースも少なくありません。
私たちにご相談いただくお客様の中にも、「登記簿の名義が祖父母のまま何十年も放置されていた」「疎遠だった兄弟姉妹と連絡がつかず、遺産分割の話し合いが進まない」「親から相続した田畑や山林は価値がないと思い込み、何も手を付けずにいた」といったお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
さらに、管理不全の空き家を放置し続けた場合のリスクも見逃せません。近隣から苦情が寄せられたり、自治体から改善の指導や勧告を受けたりしてもなお放置を続けると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、最終的には行政代執行による強制的な解体がおこなわれ、その費用が所有者に請求される可能性もあります。
これまでは「知らなかった」で済まされていたかもしれませんが、法改正が施行された今、不動産の放置は許されない時代になりました。
相続登記の基本的なプロセス
相続登記の基本的なプロセスは以下の通りです。
1.相続人の確定:戸籍をさかのぼって全相続人を調査する
2.遺産分割協議:誰がどの不動産を取得するか合意して協議書を作成および署名押印する
3.登記申請:協議書や被相続人の除籍謄本、相続人の住民票などを添えて管轄法務局へ申請する
ひとつひとつについて詳しく解説します。
1.相続人の確定
まず「相続人の確定」では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)をすべて集める必要があります。本籍地が何度も変わっている場合は、その都度、各市区町村の役所に請求しなければならず、大変な手間と時間がかかることも少なくありません。
2.遺産分割協議
次に、相続人全員が確定したら「遺産分割協議」を行います。房総の土地と家は長男が、預貯金は次男が、といったように、誰がどの不動産や財産を取得するのかを相続人全員で合意し、「遺産分割協議書」という正式な書類を作成します。この協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があり、印鑑証明書も添付します。
3.登記申請
そして最後に、作成した遺産分割協議書や、収集した戸籍謄本一式、相続人全員の住民票などを添えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ「登記申請」を行います。提出する書類は多岐にわたり、一つでも不備や記載漏れがあると申請は受理されず、何度も法務局へ足を運ぶことになりかねません。
これらの手続きをご自身でおこなうこともできますが、けっこうな時間と労力がかかるのが実情です。そこで多くの方が、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼します。専門家に依頼することで、煩雑な書類収集や作成の手間を省き、ミスなく確実に登記を完了させることができるため、検討してみる価値は十分にあるでしょう。
私たち「東栄建設株式会社」のワンストップサポート
私たち、東栄建設株式会社は以下のようなワンストップサービスを提供しています。
●提携司法書士と連携して戸籍収集から登記申請まで丸ごと代行
●登記完了後は売却・賃貸・買取など目的に応じた活用策を提示
●老朽化した空き家の解体および管理、農地や山林の活用相談に対応
千葉県房総エリアの不動産に詳しい専門家がワンチームで動くため、手続きと活用プランを同時並行で進められます。
相続登記の義務化で、不動産の放置はリスクそのものになりました。固定資産税を払い続けるだけでなく、過料や将来の行政処分まで背負い込む前に、現在の名義を確認し、3年以内の登記申請を計画してください。
千葉県房総エリアの不動産に熟知している当社「東栄建設株式会社」なら、地域特有の事情を踏まえた最適なアドバイスと手続きをご提案できます。「相続した不動産、名義はどうなっている?」と気になったら、ぜひお気軽にご相談ください。